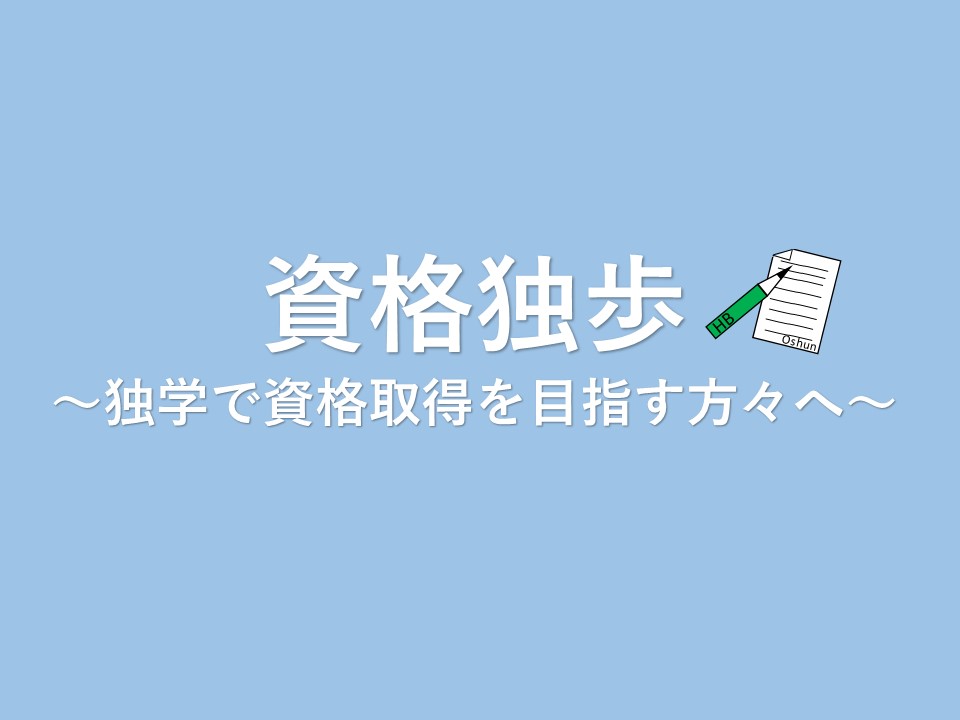普段は大学で研究をやっています。
大学の研究者と一言で言っても様々です。文系か理系かによっても大きく違います。理系の中でも生物学、物理学、化学、宇宙など分野間によっても変わります。
さらに私の行っている生物学の研究においてはウェット(wet)の研究、ドライ(dry)の研究にも分かれます。
ウェットのイメージは主に実際に実験をして結果を解析していく研究です。一方でドライはコンピューターを使って解析していく研究です。
ウェットとドライ両方が組み合わさって研究はできていくものですが、ウェットがメインの研究か、ドライがメインの研究かによって普段の研究者としての過ごし方は変わってきます。
前置きが長くなりましたが、研究者(n=1)がどんな生活しているか、これからどういう生活をしていこうか書いてみます。
私はウェットの研究が多く、そんなにきっちり時間を決めて仕事をしているわけではないのですが、多くの日は以下のスケジュールで仕事しています。
朝8時〜9時:出勤
9時~お昼頃:実験
お昼休憩30分~1時間
13時頃~17時実験
17時頃~データ整理、論文読む、研究計画立てる
20時頃:退勤
そのあと家に帰ってから余力のある日は発表用の資料を修正したり論文の整理したりしています。
土日も行くことはあります。平日に実験を開始し、◯日後に解析などでちょうど土日に重なってしまう場合や、細胞培養している場合はその世話などに行く必要が出てきます。
土日もやるかどうかは個々のワークライフバランスによります。研究者は昼夜関係なくやるべきだという意見もTwitterなどでは時折見かけますが、働きすぎて潰れたら意味がないので上述のサイクルをベースに調整しています。
今から研究者を目指す人は土日もやらないといけないのかと思われるかもしれません。平日も土日も仕事に追われながらも、やらされてる感覚よりは自ら進んで取り組んでる感覚に近いので、ある程度好きでやるのが大事だと思っています。
仕事内容的には今のところ大学院の頃と大きくは変わってはいません。今までと同じように実験したり、論文読んだり、発表したり、他の人に教えたりが日々の仕事です。これから新しい仕事もどんどん増えていきそうなのでそこは不安が半分、楽しみが半分です。
私が大学院生の時から気をつけているのは休まずコンスタントに続けていくことです。最悪どうしてもしんどくなったら休もうという選択が頭にあったのが大学院の頃でしたが、社会人としてコンスタントに仕事を続けることをまず大事にしています。研究者という仕事の性質上忙しい日や時期は出てくるので、それを見越して毎日オーバーワークにならないように調節もしています。
また、好きな研究をしながら毎月お給料がもらえるのは幸せなことだと日々感じています。大学院生の頃はバイトでいただくお給料のみで生活しており、研究とのバランスを取るのが難しかったです。
特に夜にバイト行こうと思うとそれまでに実験を絶対に終わらせないといけないという制約が出てきます。でも実験していると思わぬトラブルもあるのでバイトまでに終わらせられず何度も悔しい思いをしました。また、そもそもバイトがある日は1日がかりの大きい実験は入れられないので、バイトを増やせば増やすほど研究計画に制限が出てきて研究が遅れていきます。
下記でも書いたのですが、D3の頃にJST次世代に採択されて半年間だけ経済的に救われた時期もありましたが、博士課程の一年間は留年を経験したり、かなりアップダウンの激しい生活をしてきました。
JST次世代採択→修了→留年へ
博士課程留年の1年間のまとめ
それが今は研究をすることでお給料をもらえるので、バイトしなくても自立して生活できると思えると嬉しく、研究の一つのモチベーションになっています。
だだ、研究成果を出していけるかどうかの不安はあります。でももうその辺は考えても仕方ないので流れと運に任せつつ、とにかく精一杯やりつつ健康に過ごすのが一番だと思ってます。
また、アカデミアで研究を続けるにあたって同じような道を進む知り合いは少ないことが多いです。同年代の研究者の仲間を増やしていくためにも学会に参加して様々な方と交流していくのも研究者の仕事の一つです。
学会で発表できるように日々の研究も頑張ろつと思えるので学会に参加することでモチベーションも上がることにもつながります。
他にも大学院や研究、資格関連の記事を沢山書いてますので、そちらもぜひご覧ください。