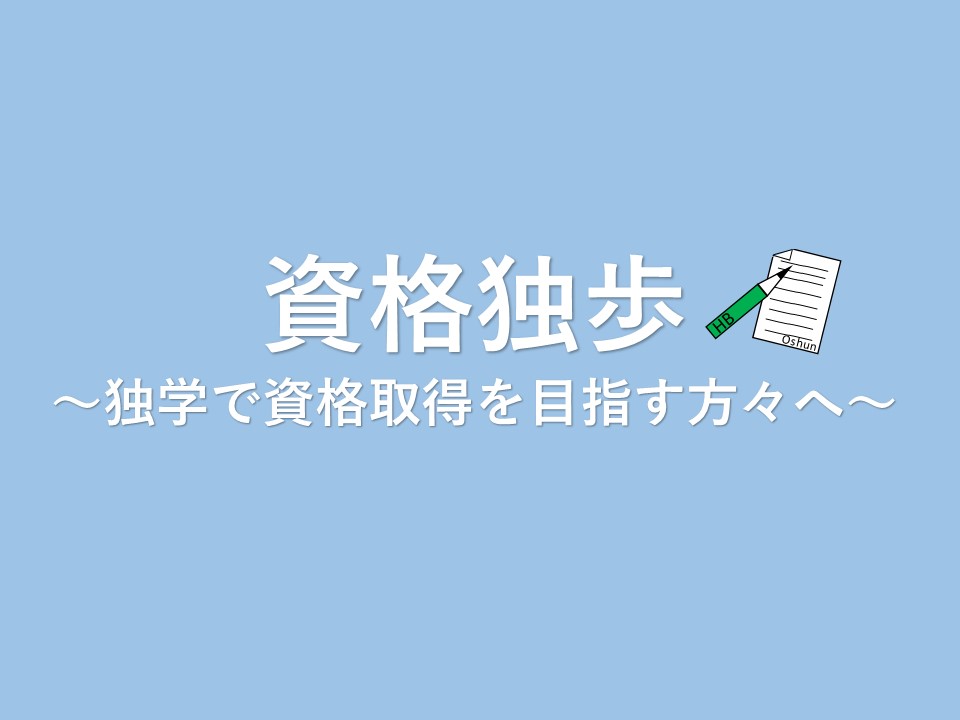本ブログをご覧いただきありがとうございます。
普段はアカデミアの研究者として働いていますが、趣味で様々な資格取得にチャレンジしています。
何のために?と言われることもありますが、単純に知らないことを知ることで世界が広がるのが面白いのが一つの理由です。
宅地建物取引士(宅建士)について身近に感じるようになったのは家の賃貸の契約の時です。その時にいわゆる重要事項説明を受けて35条書面と呼ばれる重要事項説明書を受け取りました。また契約後には37条書面と呼ばれる契約書を受け取りました。
今でこそそれぞれの違いや書いてある内容が理解できるようになりましたが、その時は何となく聞いて理解はしているものの今から考えると軽く聞き流してしまっていた部分も多いです。
きちんと理解した上で改めてもらった書類を見返すとその時には気づかなかった細かい特約なども結構書いていたことにも気づきました(おそらく説明は受けたはずですが…)。また今後引っ越したり、家を購入したりする際はどういう項目が大事なのか、どういう基準で選んでいくか、知識があるのとないのとではやっぱり見方が変わってくるように感じたのです。ちょうど昨日も住宅の売買の広告がポストに入っていましたが、どういう条件の物件か興味がわくようになりました。
そんなこんなで宅建士の勉強を始めました。目をつけ始めたのは去年の10月でしたが、ちょうど試験が終わったところで今から勉強してもなあ、と思いつつ興味は持っていたものの特にこれといった勉強はせず気づいたら今年の7月でした。
今からは厳しいんじゃないか、という話も目にしつつとりあえず申し込み締切の7月末まで勉強してみて手応えありそうなら受けようと決めて勉強し始めました。
FP2級の勉強をしていたこともあり(、税金や住宅のこと、保険のことなど基礎的な知識はある程度知っていたこともあり、割と理解はスムーズに進みました。そして7月下旬に一回過去問を解いてみたところ26/50で半分でした。合格ラインは年度によって変わりますが、37点前後ですのでもちろん26点では落ちるので全然ダメなのですが、あと3ヶ月勉強してなんとか合格したいという気持ちで思い受けることにしました。
ちなみにFPについてはオススメ記事は【FP3級FP2級対策】6つの係数それぞれの覚え方&6つの係数4択クイズの記事です。ライフプランニングで必ず出てくる内容なのでこちらもぜひご覧ください。
さて今が8月でまだ合格できるほどの力があるかというとうーん、といった感じてどうなるかわかりませんし、趣味の延長とはいえこんな記事書いて落ちると少し恥ずかしい気もしますが、合格目指して頑張ろうと思います。
最後に私が宅建士の勉強をし始めてすぐの頃に興味を持った内容を3つほど紹介します。
まず1つ目は良く住宅の広告で目にする駅から徒歩◯分の表示。これ実際本当かな?みたいに思うこと多いと思うのですが、あれは道路距離(直線距離ではなく)で80mごとに1分とし、端数の距離は繰り上げて1分とすると決められているのです。例えば駅から210mの距離だとしたら徒歩3分になります。ただし信号や踏切など他の要因は加味されていないので実際に歩くと表示内容より時間かかるなあ、となったりわけです。
2つ目は賃貸借契約の時の報酬、いわゆる仲介手数料についての決まりです。媒介する宅建士は貸主と借主からそれぞれ原則は賃料の0.5ヶ月分+消費税の分が限度です。ただし依頼主が承諾すれば一方から賃料1ヶ月分+消費税分までは報酬の受け取りが可能です。私も前回家を借りた時は1ヶ月分の仲介手数料を支払ったのですが気づかぬうちに?同意していたということです。ただ0.5ヶ月分までと主張してもじゃあ契約不成立となるだけなので仕方ない気もしますが…
最後に3つ目は宅建士しかできないことです。それは重要事項説明と重要事項説明書への記名、そして契約者への記名です。また重要事項説明をする際は宅建士証を提示する必要があります。
他にも相続や住宅ローン控除についてなど興味深い内容が沢山あり、日常生活にも少なからず役立てることができるのが宅建士の勉強の魅力です。仕事として考えても独占業務がある魅力的な資格だなと感じました。
10月に結果報告の記事も書く予定ですが、一応このブログは経験や勉強方法だけでなく、勉強中の方に役立つよういくつか宅建士の勉強の記事も書ければと思います。