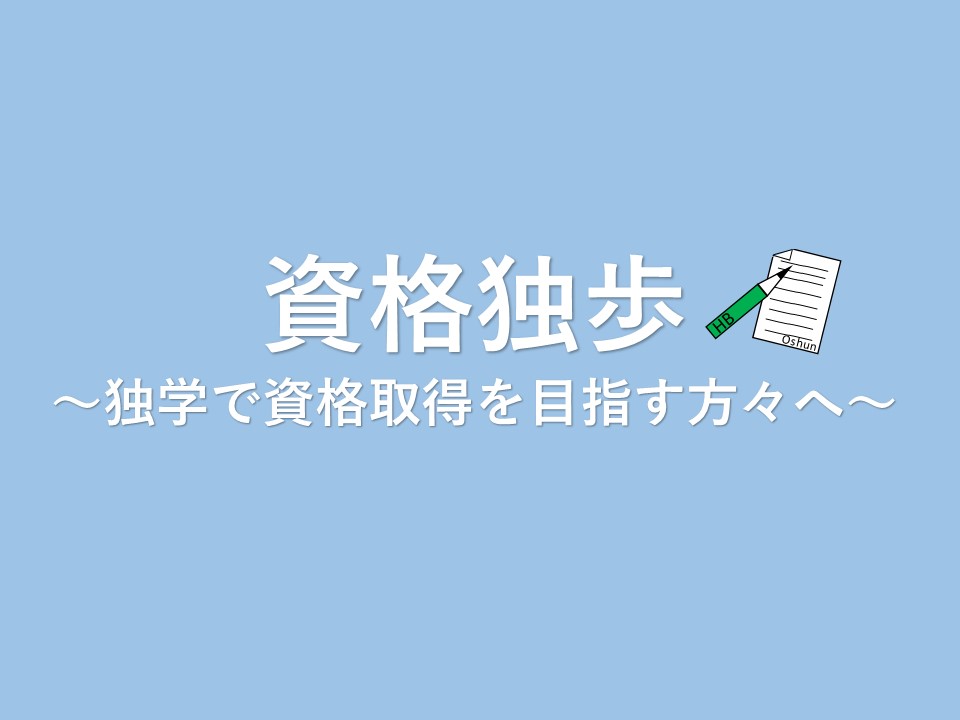はじめに
今回は特別用途地区と特定用途制限地域について解説します。
各都道府県では都道府県知事により都市計画が定められており、都市計画区域、準都市計画区域が決められております。さらに都市計画区域の中には市街化区域と市街化調整区域、そのどちらでもない非線引き区域があります。
さらに市街化区域には用途地域と呼ばれる13種類の地域を定めなければなりません。
今回解説する特別用途地区は用途地域の中に定めることができるもの、一方特定用途制限地域は用途地域以外で定めることができるものという大きな違いがあり、宅建の試験でもよく出題され混乱すると思います。では具体的にそれぞれの違いを見ていきます。
特別用途地区
用途地域内に定められますが、その種類は特に何種類とは決められていません。用途地域の制限を強化したり緩和したりするものとして用途地域のルールをさらにガチっとしたものです。各市町村の条例で決められてますが、具体的にどんなものがあるか見ていきます。
例えば東京都港区では特別工業地区、文教地区、中高層階住居専用地区が定められています(参考:https://www.city.minato.tokyo.jp/toshikeikaku/toshikeikaku/youtochiiki/tokubetsuyoutochiku.html)。大阪市では工業保全地区、中高層階住居専用地区、国際観光地区が定められています(参考:https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000611/611517/tokubetuyoutotiku-R3.11.pdf)。
港区で定められている特別工業地区は名前の通り工業に特化した地区なので、それにふさわしくない建物は規制しましょうということです。また、大阪市で定められている工業保全地区は工業機能の維持・保全のためとなっています。ちょうど今(2025年)の万博会場となっている夢洲地区の一部も工業保全地区に指定されています。
また、文教地区はこちらも名前から想像できる通り教育や文化施設が集まっているところで、教育に悪そうなパチンコ店などの建設は規制するといった地域です。港区では第一種文教地区、第二種文教地区が定められており、第一種文教地区の方がルールが厳しくなっています。港区では第一種文教地区ではホテルや旅館、映画館などが規制されています。
中高層階住居専用地区は港区だけでなく大阪市でも定められています。住宅の確保を図るためのもので、大阪市では第一種では4階以上、第二種では5階以上に建築できるものは原則住宅や公共的な施設、公益上必要な施設のみとなっています。一定階以下についてはその地区にしていされた用途地区に従う、としています。
国際観光地区は国際観光拠点にするための環境を維持・保全するための地区でこちらも大阪市では夢洲の一部が指定されています。
このように各自治体で定められているのが特別用途地区です。具体的な中身まで宅建対策としてすべて覚える必要はないですが、興味のある地域について調べてみると都市計画への理解が深まるのではないかと思います。
特定用途制限地域
次に特定用途制限地域です。こちらはさきほどとは逆に用途地域以外に定める地域です。地域の特性に応じて適切な土地利用と、良好な居住環境を形成し、保全するために建築物に規制がかけられます。例えば和歌山県紀の川市(https://www.city.kinokawa.lg.jp/037/2020-0226-1512-48.html)を見てみましょう。紀の川といえば高速道路のサービスエリアが有名なところです。
紀の川市には自然保全地区、農住共生地区、産業業務地区の3つの地域が指定されています。例えば自然保全地区では自動車修理工場やボーリング場、ホテル、旅館、自動車教習所といった様々な建物が規制されています。農住共生地区や産業業務地区でも同様に規制がかけられています。細かい内容を覚える必要はないので割愛します。
まとめ
問題として出題される一番のポイントは用途地域内か用途地域外かという点です。ただ、毎年何が出るかは未知です。試験に合格することももちろん大事ですが、特に自分の身近な地域については詳しくなっておくと実生活にも活かされると思います。私もさらに興味がある地域については調べて宅建試験に臨みたいと思います。
私が宅建を勉強するきっかけについては下記で書いてますので、こちらもぜひご覧ください。
アカデミア研究者が2025年度宅地建物取引士試験(宅建士)合格を目指す話