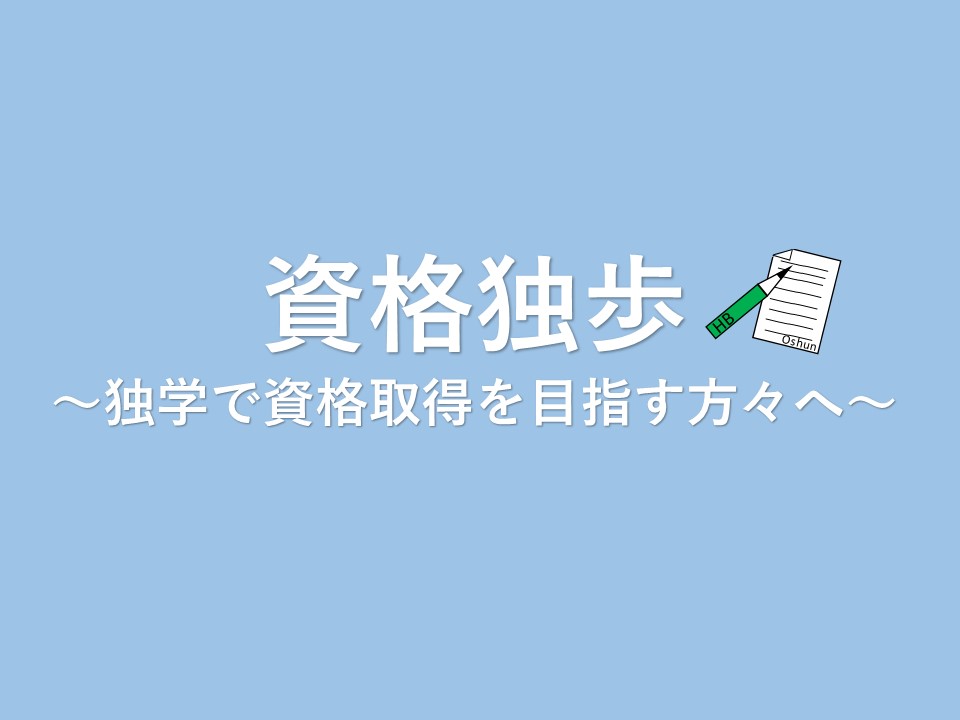現在アカデミアで研究者として働いております。アカデミアの大変さも日々痛感していますが、充実感はあり今の環境に感謝しかありません。
さてタイトルだけ見ると不真面目な学生のように思われる方もいるかもしれません。ただ、博士課程ではよくある留年、単位取得満期退学(単位修得退学と呼ぶこともある)を経験しました。そしてその後無事に博士の学位を取得しました。今回はこれらを経験して思ったことを書いてみたいと思います。留年、満期退学したことに関して今はネガティブな感情はなく、むしろポジティブな話として見ていただけると嬉しく思います。
以前に留年が決まって思ったこと(下記)についても書いていますのでぜひご覧ください。
博士課程留年が決まって思うこと①
まず私は博士課程3年を終えた頃に論文をサブミット(投稿)できませんでした。それはもう3年の初めの頃には難しいだろうなとわかっていたことですが、今の研究テーマをまとめるには時間が足りないと気づきました。しかし、中途半端な状態で論文を出すよりも限界までやりきりたいという思いや、そもそもどんな研究テーマも博士課程の決められた3年(研究科によっては4年)できれいに終わること自体が難しいことだと思っていたので、案外すんなり受け入れることができました。
まずこのタイミングで留年するか満期退学にして就職する選択肢も出てくると思います。留年するメリットは大学院生の身分として研究を続けることができること、なのですが、これに何のメリットがあるのだろうかと思われる方も多いかもしれません。
博士号には課程博士と論文博士があります。課程博士は簡単に言えば大学院生としての課程を修めて博士論文を出して博士号を取る道で、論文博士は博士課程としては在籍せずに論文を通して博士号を取る道です。企業に在籍しながら大学で研究して論文を出す時は論文博士として学位を取るパターンが多いのではないかと思います。ただ、課程を修めても必ず課程博士になるかというとそうではなく、大学や学部によってルールは異なると思いますが、満期退学してから〇年以内に論文を通すことが条件になっていることがあります。つまり課程中に博士号を取れずに、満期退学後に課程博士として博士号を取るためにも期限があるのです。本来は3年以内に博士号を取れればもちろん良いのですが、そうでない場合に課程博士が取れる期限も考える必要が出てきます。仮に留年した場合は大学院生としての生活が続くことになり、満期退学後〇年という期限に向かうカウントダウンも遅らせることができます。せっかく課程を修めたので、課程博士が良いかなと思っていたことや論文博士になると博士号の条件が変わってしまうこともあり、私の場合は課程博士として博士号を取得したいと思っていました。いくらなんでも満期退学した後に学位取得までそんな時間かかることなんてないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、後に書きますがこの選択によって私がギリギリ課程博士に滑り込めることとなったのです。
もちろん満期退学して期限内に論文を出せることが一番良いのですが、論文を早く通したくても投稿した論文が返ってくるまでに時間がかかったり、と自分の力だけではどうしようもない部分もあります。そういう意味で満期退学も安易に選ぶのは少しリスクがあると当時は考えました。また、満期退学するということはどこかに雇ってもらう必要が出てきます。もう博士号取得が見えて来ていれば考えも変わったかもしれませんが、私の場合はまだまだその段階には至っていませんでした。
もちろん留年の方にもデメリットもあり、それは学費が発生するということです。大学院が1年延びるので、追加で1年分学費を払う必要があります。それに加えて生活費の問題です。満期退学して働きながら博士号を目指すという道であれば生活との両立ができる可能性もありますが、生活できない状況であれば留年を選ぶことも難しくなります。幸いだったのは私は留年しながら臨床検査技師の資格を活かしてアルバイトをしていたこと、またありがたいことに家族のサポートも得られていたので留年を選択することができましたが、留年を選ぶ場合はそこもよく考える必要はあります。
また、皆様は留年という言葉にどんなイメージを抱くでしょうか。博士課程の事情を知らない場合は留年というとなんとなく印象悪く思われてしまいがちです。規定年度で卒業できることは素晴らしいと思う反面、博士論文を良い形に仕上げるにあたって留年という選択は挑戦的と言っても良いと個人的には思っています。
長くなりましたが、色々考えた結果、私は1年間留年を選ぶことにしました。その選択をさせてくれた家族には感謝しかありません。成果を出すことが家族への恩返しにもなると思い研究に励みました。そして4年目が終わり、論文をサブミットするところまでは到達することができました。しかし、博士号を取るためには論文がアクセプトされて、出版され、さらに学位審査に合格する必要があります。つまり4年目にサブミットでは全然間に合っていないというわけです。そこで、5年目をどうするかという選択をする必要が出てきました。
研究が3年目の頃よりも大きく進展し、学位に向けて大きく前進したこともあって、幸い大学内で働く機会をいただくことができました。自分としてもゴールが少し見えてきて課程博士として間に合うだろうという気持ちもあったので、満期退学を選択することにしました。満期退学は博士課程の単位は全部取ったけれども論文がアクセプトされていないため一般的な退学とは区別して単位修得退学や単位取得満期退学と呼ばれたりしています。この時にはもう目の前の論文のことしか考えることもなくなり、周りにどう思われようとも論文を通すことしか頭にありませんでした。大学内で働きながらでしたので、大学院生の頃と変わらず研究はやりやすかったこともあり、早く論文をアクセプトさせたい気持ちで毎日実験に明け暮れていました。
そして、論文を出されたことがある方はご存じの通りですが、論文をサブミット(投稿)した後はすぐにアクセプト(採択)されパブリッシュ(出版)されるということはまずありません。多くの場合はまずエディター(編集長)がリジェクト(不採択)の判断をするか、レビューワー(査読者)に論文を回すことになります。その後レビューワーからのコメントが返ってきて、それに対応するために追加実験を行う必要が出てきます。それに対応してから再度サブミットし、レビューワーが再度コメントをして、それに対応して・・・ということをしていく必要があり、その結果最終的にアクセプトされるかどうかが決まります。
つまり言いたいのはサブミットからアクセプトまではかなり時間がかかるということです。この間妻には大変苦労をかけてしまい支えてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです。いつ論文が返ってくるかわからない上に、いつまでに再度サブミットする必要があるか期限が決められているため、妻との予定も急に変更する必要が出てくることが多くなりました。そして、アクセプトまでにそれなりに時間を要しましたが、無事にアクセプトまで到達することができました。ここまでにもかなり時間がかかってしまいましたが、そこから次は学位審査があります。アクセプトされた論文を元に学内で審査してもらい博士号を取得できるかどうかが決まります。
かつての自分なら学位審査に対して不安や緊張もあったと思いますが、留年や満期退学を経験して成長を実感できており、何より長らく自分の研究をやってきたこともあったので、程よい緊張感で自信を持って審査に臨むことができました。学位審査にもそこそこの時間を要したのですが、無事に合格することができ、博士号を取得することができました。
そして、博士号を取得した頃には満期退学後に課程博士として博士号を取る期限のギリギリでした。ここまで時間がかかるとは博士課程に入学した頃、さらには留年、満期退学を選択した頃でさえも想像しきれていませんでしたが、ただ、自分が好きな研究を最後までやり遂げたいという思いが叶えられたことで、満足感も大きかったです。また、支えてくれる人がいなかれば成し遂げることはできなかったとも思いました。さらに、アカデミアで研究する面白さも実感することができ、結果的に今もアカデミアで研究を続けるきっかけになりました。
結果的にではありますが、博士課程は留年、満期退学しても納得いくまでやりきって論文を通して博士号を取得すれば、その間に得られるものも大きいということを実感した経験でした。この経験が今同じように境遇にある方々の参考になれば幸いだと思っています。