大学院入試の季節になってきました。夏から秋にかけて大学院入試は行われ、試験科目は大学や研究科によってバラバラですが、英語についてはどこの研究科に行くにしても必要にはなってくることが多いです。筆記試験を行うところもあれば、TOEICやTOEFLといった試験で代用していることもあります。
今回は筆記試験の英語を行うタイプの大学院入試の英語対策についてお話しします。まずシンプルな対策方法ですが、研究室の先輩などに過去問などをもらっておくことが1番大事です。外部から受験する大学院生も事前に研究室に見学には行くと思うので、その時にもらえたらもらった方が良いです。そこでどういう問題が出るのかを把握しておくことが必要です。
そして、その過去問を見てそれに合わせてもちろん勉強し、問題の傾向をつかむ上では大事ですが、個人的にはあまり過去問を解くことに躍起になる必要はないかなと思います。むしろ実際の英語の対策は研究室に関連する論文を読むのが効果的です。英語の勉強としては広くいろいろな分野の英語を読むことも大事ですが、どうせ勉強するなら研究室に入ってからも活かせる方が圧倒的に有利になります。それをやることによって英語を読むトレーニングにはなりますし、論文でよく使われる英単語はある程度共通しているので勉強にはなります。その論文を使いながら過去問の形に合うように学べるのが理想的だと思います。
次に実際に研究室に入ってから必要な英語力ってどれくらいなのかについてお話しします。
研究室では論文を読めないと研究を進めることが難しいです。ただ、最近はAIが発展しているので簡単に日本語で内容を読みとることはできます。じゃあ英語読めなくても良いのか?というとそれでは難しい場面もあります。常にAIで翻訳しながら議論をできるわけではないので、ミーティングなどの際に論文を参照しながら議論する場合は英語がわからないとついていけないことがあります。また、実験で海外の製品などを扱うことも多々あるので、ちょっとした英語のプロトコルなどもそのまま読めた方が円滑に研究を進めることができます。
国際学会などで発表する機会があればSpeakingやListeningの練習も必要になってきますが、大学院に入るまでに英語をペラペラにしておかないといけない、というほどではないとは思います。私も今も勉強中ですが、聞いたり話したりがスムーズにできればより多方面で活躍はしやすくなるとは思います。
Writingについてはこれも最近ではAIが大活躍してます。私も自分の英語の添削にはよく使っていますし、ある程度文法がわかっていれば書くことはできると思います。
これらの話をまとめると大学院で必要な英語力は圧倒的にReadingの力にはなってきます。論文は毎日読むと言っても良いので、概要をつかむためにAIは非常に役に立ちますが、細かい部分は自分で読めるほうが良いかなと思います。
大学院入試の英語対策と大学院で実際に必要な英語力
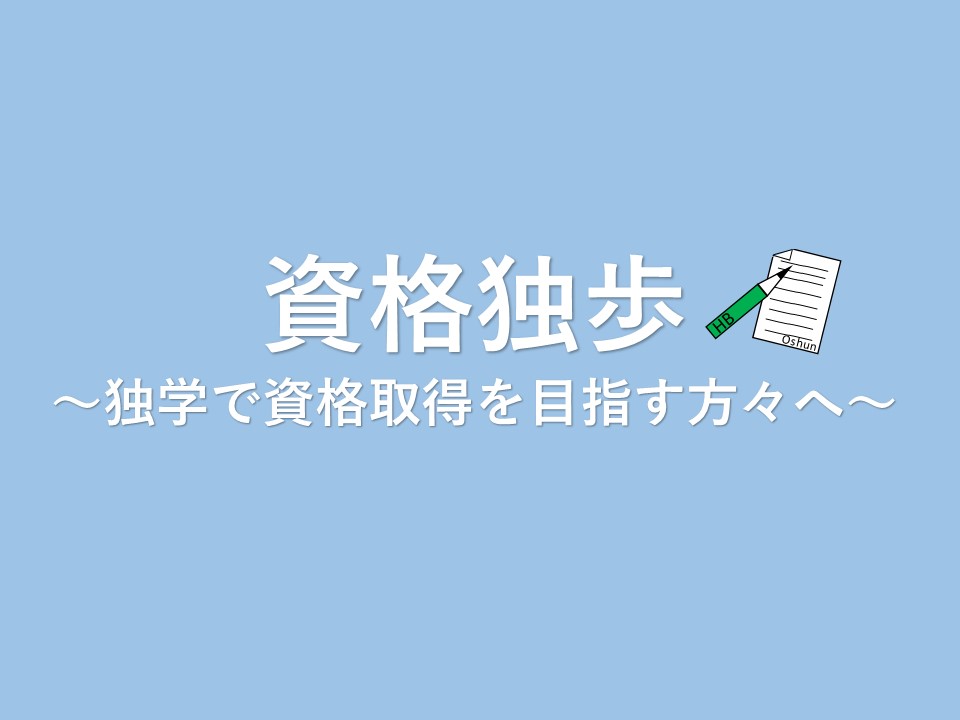 大学院/研究
大学院/研究